コラム
リモートワークには社内SNSが効果的!例文と運用のコツを紹介
テレワークやハイブリッドワークが定着する一方で、「従業員同士の顔が見えない」「業務以外の会話がまったくなくなった」という課題を抱える企業が増えています。そこで、組織の一体感を取り戻すツールとして注目されているのが「社内SNS」です。
ビジネスチャットのような業務連絡ツールとは異なり、社内SNSは「人」や「感情」にフォーカスしたコミュニケーションを生み出します。本記事では、リモートワークで社内SNSが効果を発揮する理由や、盛り上がる投稿の例文、形骸化させないための運用のポイントについて詳しく解説します。
![]()
![]()
![]()
リモートワークに社内SNSが効果的な理由

リモートワークでは、オフィスで自然に行われていた「挨拶」や「立ち話」がなく、業務連絡のみの無機質なやり取りになりがちです。そのようななかで、フロー型のチャットツールとは異なる、ストック型のコミュニケーションが可能な「社内SNS」の注目度が高まっています。なぜ今リモート環境に社内SNSが必要なのか、その導入効果を5つの視点で解説します。
雑談が生まれ、コミュニケーション不足が解消する
ビジネスチャットは「業務連絡」が主な目的であるため、「これくらいのことで連絡していいのだろうか」と躊躇してしまい、雑談が生まれにくい傾向にあります。リモートワークで雑談がなくなると、孤独感が深まり、メンタルヘルスにも悪影響を及ぼしかねません。
社内SNSは、業務とは直接関係のない話題や、個人的なつぶやきを発信することに特化しています。「今日のランチがおいしかった」「昨日始まったドラマがおもしろかった」といった業務に関係ない会話が許容される場があることで、従業員の心理的なガス抜きになります。こうしたつながりが潤滑油となり、結果として業務上のコミュニケーションも円滑に進むようになるのです。
ナレッジやノウハウが資産として蓄積される
チャットツールやメールでのやり取りは、時間が経つと流れてしまい、後から情報を探すのが困難です。特にリモートワークでは、隣の席の人に「あれどうやった?」と気軽に聞くことができないため、個人のノウハウが属人化しやすいという大きな課題があります。
社内SNSはストック型の情報共有に適しており、投稿された成功事例やトラブルシューティング、業務のコツなどが検索しやすい状態で蓄積されていきます。そのため、新入社員や中途入社者が過去の投稿をさかのぼって自律的に学べます。個人の頭の中にあった知見が「会社の資産」として可視化され、組織全体のスキル底上げにつながる点は、経営視点でも大きなメリットです。
部署を超えた横のつながりが生まれる
リモートワーク環境下では、どうしても自分が所属しているチームや直属の上司とのやり取りだけに閉じてしまいがちです。他部署がどのような仕事をしているのか、どんな人が働いているのかが見えにくくなり、組織のサイロ化が加速してしまいます。
社内SNSのタイムラインは、全従業員に対してフラットに開かれています。普段関わりのない開発部のリリース報告や、営業部の受注報告、総務部のお知らせなどが自然と目に入ってくるため、部署の壁を越えた情報共有が実現します。そうしたつながりから「この件なら、あの部署の〇〇さんが詳しそうだ」といった認知が広がることで、新たな社内コラボレーションや、部門を横断した協力体制が生まれやすい土壌が育ちます。
人となりが伝わり、信頼関係が深まる
テキストだけのコミュニケーションでは、相手の感情や性格が伝わりにくく、些細な言葉の行き違いで不信感を抱いてしまうことがあります。特に、一度も対面したことのないメンバー同士の場合、信頼関係を築くのには長い時間を要します。
社内SNSは、プロフィール欄の充実や日常の投稿を通じて、その人の趣味、家族構成、大切にしている価値観などの「人となり(コンテキスト)」を知ることができる場です。「この人は子育て中だから夕方は忙しいんだな」「キャンプが好きという共通点があるな」といった背景情報の共有のよって親近感が湧きます。相手を「アイコン」ではなく「人間」として認識できるようになることで、業務上の依頼や相談もしやすくなり、チームビルディングが促進されます。
経営理念や経営層の想いが浸透する
リモートワークでは、オフィスの壁に貼られたスローガンを目にすることもなければ、朝礼で社長の熱量を感じる機会も減ってしまいます。その結果、会社がどこを目指しているのかが見えなくなり、帰属意識が低下してしまうリスクがあるでしょう。
社内SNSを活用すれば、経営層が自身の言葉で、会社のビジョンや日々の想いを全従業員に直接届けることができます。社内報のような一方的な配信とは異なり、従業員が「いいね」やコメントでリアクションできる双方向性が特徴です。経営層と現場の心理的な距離が縮まり、「自分たちは同じ船に乗っている」という一体感が醸成されるため、理念に基づいた自律的な行動が増えていきます。
リモートワークで盛り上がる社内SNSの投稿例
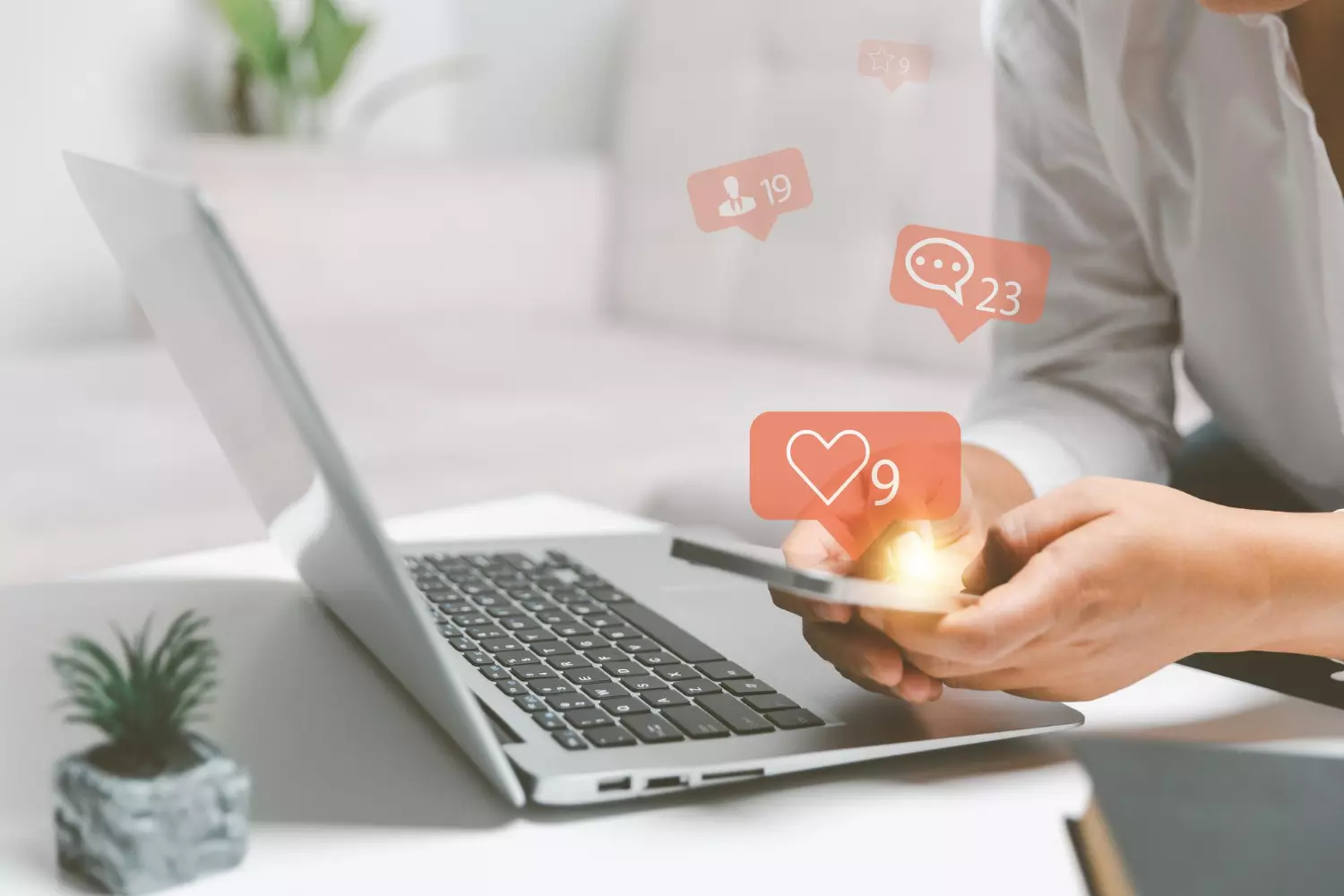
社内SNSを導入しても、「何を書けばいいかわからない」と手が止まってしまう社員は多いものです。ハードルを下げるためには、いくつかの鉄板ネタを提示することが有効です。
ここでは、リモートワーク環境下でも書きやすく、周囲からの反応が得られやすい具体的な投稿テーマと例文を紹介します。
自己紹介や趣味・特技のシェア
最も書きやすく、かつ盛り上がるのが自己紹介系の投稿です。新入社員の挨拶はもちろん、既存社員も改めて「自分の好きなもの」を発信することで、意外な共通点が見つかります。特にリモートでは視覚情報が不足しているため、写真を添えるのがポイントです。
-
はじめまして!4月から営業部に配属された〇〇です。映画鑑賞が趣味なので、おすすめの映画を教えてください!
-
我が家のリモートワーク監視員を紹介します(猫の写真)。キーボードに乗ってくるのが悩みですが、癒やされています。
-
週末はキャンプに行ってきました!焚き火を見ていると頭がスッキリします。キャンプ好きな方、おすすめのギアを教えてください。
-
仕事のお供に最高なコンビニスイーツを発見しました。糖分補給して午後も頑張ります!
-
実は学生時代にジャズピアノをやっていました。最近また練習を再開したので、音楽好きな方いたらぜひお話しましょう!
業務上の「気づき」や業界ニュースの共有
日報ほど堅苦しくなく、メモ書き程度の気軽さで「学び」を共有する投稿です。発信者にとってはインプットの定着になり、読み手にとっては有益な情報源となります。「勉強熱心な人」というポジティブなブランディングにもつながります。
-
競合他社の新しいアップデート、おもしろい動きですね(URL)。ウチの〇〇サービスにも応用できそうな気がします。
-
Excelでこのショートカットキーを知ってから、作業効率が爆上がりしました。皆さんもぜひ使ってみてください。
-
今日お客様とのZoomで、『〇〇さんの対応が早くて助かる』と褒めていただきました!嬉しいので共有させてください。
-
先日のプロジェクトで使った〇〇というツール、かなり便利でした。使い方をまとめたので興味ある方は参考にしてください。
ランチや休憩中の何気ないつぶやき
オフィスにいた頃の「給湯室での立ち話」や「ランチタイムの会話」を再現する投稿です。リモートワークでは「今、席にいるのか?」「忙しいのか?」が見えにくいため、こうしたつぶやきが「元気でやっている」という生存確認の役割も果たします。
-
今日のランチはUber Eatsで頼んだカレーです。辛さを5倍にしたら汗が止まりません(笑)。午後眠くならないように気をつけます。
-
集中しすぎて肩がバキバキなので、15分ほど散歩してきます!外の空気を吸ってリフレッシュします。
-
こっちは急に雨が降ってきました。皆さんの地域はどうですか?洗濯物が心配です…。
-
午後の会議に向けてコーヒーブレイク中。みなさん午後も頑張りましょう!
社内SNSを形骸化させない運用のコツ

社内SNS導入における最大のリスクは、最初の数ヶ月だけ盛り上がり、徐々に投稿が減って「廃墟」となってしまうことです。リモートワーク下で、継続的に活気ある場を維持するためには、運用ルールや雰囲気作りが重要です。そこで、担当者が押さえておくべき3つのポイントを解説します。
ビジネスチャットとの使い分けを明確にする
多くの企業で失敗する原因の一つが、SlackやTeamsなどの「ビジネスチャット」と「社内SNS」の使い分けが曖昧なことです。「どっちを見ればいいのかわからない」「同じ内容を二重投稿するのが面倒」となると、従業員は次第にSNSを見なくなってしまいます。
「緊急連絡や業務指示はチャット」「称賛・雑談・ナレッジ共有はSNS」というように、ツールの目的と役割を明確に定義しましょう。たとえば、チャットの雑談チャンネルを廃止してSNSに一本化するといった方法も一つの手です。ツールごとの住み分けをガイドライン化し、周知徹底することが定着への第一歩です。
経営陣やマネージャーが率先して自己開示する
新しい文化を根付かせるとき、最も影響力があるのはリーダー層の行動です。上司が「業務に関係ないことは書くな」という雰囲気を出していたり、自身が全く投稿していなかったりすると、部下は「こんなことを書いて怒られないかな」と萎縮してしまいます。
まずはマネージャーや役員が率先して、失敗談やプライベートな一面、弱みをさらけ出すことが重要です。「部長も週末はゴロゴロしているんだ」「社長も昔はそんな失敗をしたんだ」と分かることで、心理的安全性が高まり、メンバーも安心して投稿できるようになります。リーダーは「監視役」ではなく「盛り上げ役」になる意識を持ちましょう。
「見るだけ(ROM専)」を許容し、強制しない
全従業員に毎日投稿を義務付けると、SNS自体が業務上のノルマとなり、ストレスや「やらされ感」を生んでしまいます。結果として、内容は薄くなり、義務的な投稿でタイムラインが埋め尽くされてしまうでしょう。
SNSには、積極的に発信する人もいれば、見るのが好きな人(ROM専)もいます。発信頻度を評価に直結させるような強制は避け、「見るだけの人も歓迎」「いいね!を押すだけで参加とみなす」という緩やかなスタンスで運用しましょう。誰かに強制されるのではなく、「楽しいから見る」「役に立つから書く」という自発的な動機づけを大切にすることが、長続きさせる秘訣です。
リモートワークに適した社内SNS「RECOG」

リモートワークでの社内SNS運用において、特におすすめしたいツールが「RECOG(レコグ)」です。RECOGは「サンクスカード(称賛)」の機能を中心に据えたコミュニケーションツールですが、投稿機能やチャット機能も持ち合わせており、社内SNSとしても優秀です。
「ただの雑談SNSだと上層部の理解が得にくい」という場合でも、「称賛文化の醸成」という明確な目的があるRECOGなら導入しやすく、結果として社内コミュニケーションの活性化を実現できます。
詳細は以下の資料で紹介しているので、ぜひダウンロードしてみてください。
リモートワークにおける社内SNSは、単なる暇つぶしの場ではなく、組織の「心理的安全性」や「横のつながり」を維持するための重要なインフラです。 雑談や称賛を通じて互いの「人となり」を知ることで、離れていても信頼関係を築くことができます。まずはリーダーが率先して自己開示し、ビジネスライクになりがちなリモート環境に「人間味」を取り戻すことから始めてみてはいかがでしょうか。社内SNSで生まれた小さな会話が、やがて大きな組織力へとつながっていくでしょう。 \\編集部おすすめ記事//
まとめ

















