コラム
サンクスカードの導入目的とは?達成のための成功ポイントを紹介
サンクスカードの導入目的は、コミュニケーション不足の解消や離職率低下など、企業ごとに内容が異なります。導入目的を達成するには、どのような点を意識すべきでしょうか。
本記事では、サンクスカードの導入目的や達成に向けたポイントなどを紹介します。サンクスカードの導入を検討している方は、参考にしてみてください。
サンクスカードとは

サンクスカードとは、従業員同士が互いの仕事ぶりやサポートに対して、自発的に感謝や称賛の気持ちを伝え合うカードです。紙のカードやアプリなどを使って、メッセージのやり取りを交わします。
従業員同士がサンクスカードを通じて互いを評価・称賛し合うことで、従業員の相互理解や信頼関係が深まります。
サンクスカードの詳細については、こちらの記事で詳しく解説しています。
サンクスカード導入の主な目的

サンクスカードを導入する目的には、主に以下6つのような内容が挙げられます。
社内コミュニケーションの活性化
職場のコミュニケーション不足は、会話頻度の減少や従業員同士の理解不足、上司との距離感の遠さなど、さまざまな要因によって生じます。
サンクスカードを通じて相手の仕事ぶりに感謝や称賛する機会が増えると、従業員同士の距離も縮まり、会話の頻度が増えます。
感謝の言葉にはポジティブな作用が期待できるため、サンクスカードを贈った側と贈られた側の双方が前向きな気持ちになり、職場の雰囲気がよくなるでしょう。
また、サンクスカードの導入で従業員同士の会話が増えると、伝達ミスや共有不足が原因でのトラブルを大幅に削減できる点もメリットです。
従業員のモチベーション向上
従業員のモチベーションアップもサンクスカードを導入する目的の1つです。他の従業員からサンクスカードを受け取ると、メッセージの内容から「自身の仕事が誰かの役に立っている」と実感でき、承認欲求が満たされます。
また、自身の仕事ぶりや貢献が正当に評価されると、今後も自信をもって業務に取り組めるでしょう。自信が得られると業務へのモチベーションも高まり、パフォーマンスの向上やスキルアップの促進が期待できます。
離職率と人材定着率の改善
サンクスカードを通じて、従業員同士が互いの仕事ぶりや貢献に感謝を伝え合う文化が定着すると、離職率の低下や人材定着率の向上が期待できます。
カードに書かれた内容から「自身の仕事ぶりや貢献が認めてもらえている」と感じ、勤務先へのエンゲージメントが高まるためです。
また、サンクスカードの導入で、社内コミュニケーションが活性化されると、職場の雰囲気も明るくなります。上司や先輩、同僚に相談しやすく、安心して自身の気持ちや意見を述べられる環境が整うため、仕事で悩みが生じても早期解決が望めるでしょう。
チームワークの強化
サンクスカードの導入で従業員同士が互いを気遣うようになり、協調性が高まります。サンクスカードには、相手のどのような貢献やサポートに感銘を受けたか、具体的なエピソードの記載が必要です。
相手の心に響くメッセージを書くには、普段から相手の業務内容や仕事ぶり、行動に気を配らなければなりません。
そのため、従業員同士が互いの長所を見つけようと意識するようになり、信頼関係や相互理解が深まります。良好な人間関係の構築によって、組織全体で協力しやすい環境が整い、チームワークや部署間での連携強化が期待できます。
隠れたファインプレーの可視化
サンクスカードを導入すると、数字には表れない貢献や細やかな気配りが、組織全体で共有・評価される環境が整います。
サンクスカードは成果の大きさではなく、普段の仕事ぶりや貢献にも感謝の気持ちを伝えられるカードです。「問い合わせ対応のアドバイスが参考になりました」「納期調整ありがとうございます」など、具体的なエピソードを交えて相手に感謝の気持ちを伝えます。
カードを贈られた従業員は、メッセージの内容から「自身の仕事ぶりを評価してもらえた」と前向きな気持ちになり、業務へのモチベーションアップが望めるでしょう。
企業によっては大型案件の受注やヒット商品の開発など、目に見える成果ばかりを評価するケースも珍しくありません。ただし、バックオフィスや営業事務など、成果が数字に表れない業務を着実にこなす従業員の存在がなければ、安定した事業運営は望めないでしょう。
サンクスカードの導入で、普段は評価されにくい「縁の下の力持ち」的な貢献を果たす従業員を正当に評価し、エンゲージメント向上につなげられます。
企業文化の革新
サンクスカードの導入で「相手を称賛する」文化をつくり出せます。称賛文化が醸成されれば、組織全体で相手の短所ではなく長所を探す意識が強くなります。
サンクスカードは、相手の仕事ぶりに対して感謝や称賛の気持ちを伝えるものです。そのため、相手を加点方式で見るようになり、職場の雰囲気がポジティブに変わるでしょう。
また、サンクスカードを通じて従業員同士の信頼関係や相互理解が深まるため、部署や役職を問わず社内全体のコミュニケーションが活発になります。
会話の頻度が増えると職場全体の雰囲気も明るくなり、業務効率化や新たなアイデアの創出など、さまざまなメリットをもたらします。
企業の課題・状況別のサンクスカード活用目的

サンクスカードは企業の課題や状況に応じた活用が可能です。ここでは、3つの事例を紹介します。
リモートワーク環境でのコミュニケーション補完
サンクスカードは、リモートワークで発生しがちなコミュニケーション不足を補うツールとして活用できます。サンクスカードを導入すれば、業務連絡以外で他のメンバーとコミュニケーションを取るきっかけが作れるためです。
リモートワークは、チャットやメールを利用したテキストコミュニケーションが中心です。オフィスワークと異なり、他の従業員が仕事をしている様子や手が空くタイミングが見えないため、気軽に雑談はしづらい状況です。
業務連絡や進捗状況を報告した際も、相手の状況によっては返信にタイムラグが生じるため、リアルタイムでのやりとりは難しい場合があります。
また、異なる場所で仕事をしているため、メンバーの仕事ぶりが見えにくいという傾向もあります。
上記の理由から、オフィスワークと比べてコミュニケーションを取る頻度が減るため、寂しさや孤独感、ストレスを覚える従業員もいるでしょう。
サンクスカードを導入すれば、部署やチームのメンバーとコミュニケーションを取るきっかけが増えます。コミュニケーション不足にともなうメンタルヘルスの不調を防ぐ効果も望めるでしょう。
現場と管理職の連携強化
現場の従業員同士によるサンクスカードのやりとりを見ると、管理職は現場で働く従業員がどのような思いを抱えているか、どのような貢献をしているのか把握できます。
管理職は現場の従業員同士がどのようにフォローし合っているか、すべてを把握できるわけではありません。
しかし、「○○さんのアドバイスでミスが減りました」「丁寧な指導ありがとうございました」など、後輩従業員のサンクスカードを見れば、現場の雰囲気や従業員同士の人間関係を把握できるきっかけとなります。
また、管理職から現場で働く従業員に感謝の気持ちを伝えることで、コミュニケーションの活性化や部門間の連携強化が期待できるでしょう。
ノウハウ共有によるスキルアップ
サンクスカードで感謝の気持ちを伝える際、自身のナレッジや成功事例も添えると、従業員のスキルアップを促せます。カードを受け取る側は客観的な視点から評価してもらえるため、自身では気づかなった課題や改善策を把握できる可能性があります。
たとえば、営業職で働くベテラン従業員が、成績が伸び悩む若手従業員の営業に同行したとしましょう。サンクスカードで「今日はありがとう!提案の際は、論点を絞るともっとスムーズにできると思うから頑張って!」と伝えると、相手はフィードバックを意識しながら次回の商談に臨めます。
また、他の従業員のサンクスカードを見ると、どのような行動が感謝・称賛されるのかを把握できるだけでなく、自身の業務に役立つヒントを発見できる場合もあります。
導入目的を達成するための成功ポイント
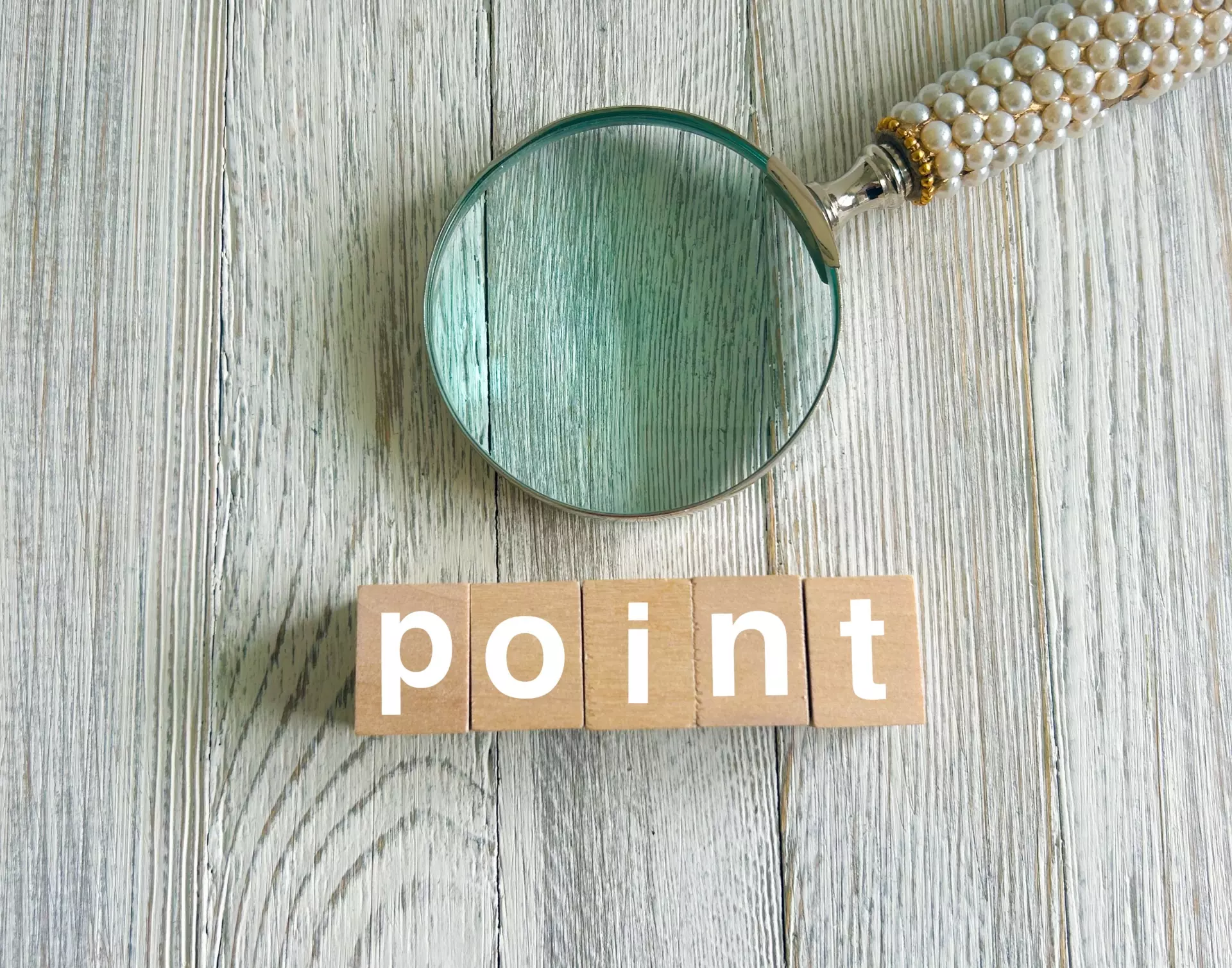
サンクスカードの導入目的を達成するためには、以下の3点を意識しましょう。
義務やノルマにしない
従業員への負担を減らすため、サンクスカードの運用ルールに「毎月5枚は贈る」「最低でも1週間に1枚は贈る」など、ノルマは設定しないようにしましょう。
ノルマを設定した場合は従業員が義務感を覚え、形式的なメッセージのやりとりに終始する傾向が強くなります。
サンクスカードの導入目的や解決したい課題などを丁寧に説明し、従業員の自発的な参加を促しましょう。
経営層・管理職が率先して活用する
サンクスカードの利用が定着するには、経営層や管理職が積極的に活用することが重要です。経営層や管理職の言動が従業員に与える影響力は大きいため、積極的に参加している姿を見せると、組織文化としてサンクスカードが浸透しやすくなります。
たとえば、管理職が総務職として働く従業員に対し、社内調整や段取りなどの仕事ぶりをサンクスカードで評価したとしましょう。サンクスカードを贈られた従業員は、自身の仕事ぶりを正当に評価してもらえたと感じます。
また、他の従業員がサンクスカードを見ると、制度にポジティブな印象をもつようになり、今後の積極的な利用が期待できます。
サンクスカードツールを導入する
サンクスカードは紙のカードを使用する方法もありますが、ツールの利用がおすすめです。紙のカードを使用するよりも、多くのメリットを得られるためです。
サンクスカードツールを活用する1つめのメリットは、場所や時間を問わず相手にメッセージを贈れる点です。
紙のカードでは業務の妨げにならないよう、カードを贈る相手の離席や業務の進捗状況を確認しなければなりません。サンクスカードツールの場合、自身の好きなタイミングで相手にカードを贈れるだけでなく、リモートワークの場合もスムーズにやり取りが可能です。
また、紙のカードを運用する場合、担当者がカードの用意や回収、保管など、さまざまな作業をこなさなければなりません。一方、サンクスカードツールを使えば、一連の作業がオンライン上で完結するため、担当者の負担を大幅に軽減できます。
さらに、サンクスカードツールの多くはデータ分析機能を搭載しており、分析結果をもとに課題抽出や改善策の実施を進められます。
手軽に感謝・称賛を贈り合うにはチームワークアプリ「RECOG」で

チームワークアプリ「RECOG」は、サンクスカードを贈り合える「レター」機能に強みをもつサービスです。パソコンやスマートフォンで手軽にサンクスカードを贈ることができ、そのサンクスカードを見た他の従業員も拍手やコメントでリアクションが可能です。
他にも、情報共有の場として活用できる投稿機能や、個人またはグループでチャットできるトーク機能も搭載。RECOGの詳細は以下の資料で紹介しているので、ぜひダウンロードしてみてください。
サンクスカードの導入目的は、コミュニケーションの活性化やチームワークの強化、離職率の低下など、さまざまな内容が挙げられます。従業員のスキルアップ促進や部門間の連携強化など、企業が抱える課題によって幅広く活用できます。 導入目的や課題達成に向けては、サンクスカードの利用を義務化しないことが重要です。ノルマを設定した場合、従業員が義務的にカードを贈り合う可能性が高まります。 また、サンクスカードツールを利用すると従業員がメッセージを贈りやすくなり、利用を促せるでしょう。 本記事で紹介した内容を参考に、サンクスカードの導入を検討してみては、いかがでしょうか。
まとめ
\\編集部おすすめ記事//
















